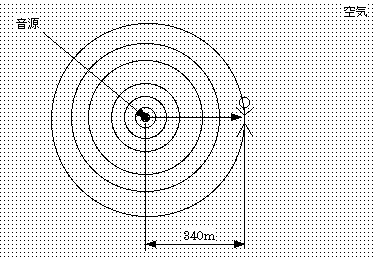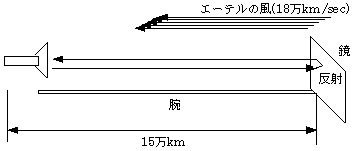題名:科学について-相対性理論と疑似科学
日付:2000/6/30
マックスウェル方程式普通マックスウェルと聞くと思い出すのはカセットテープか何かの銘柄であろうか。しかしながら、「の法則」がつくと、これは電磁気の基本的な法則を意味する。
等と書くと何かと難しそうだが、身近なところでは、携帯をバイブレーションモードにしておくと、電話の着信時に携帯が振動するのは、つまるところ電気をいれればモーターが回るからである。右手だ左手だの法則はさておいて、とにかく電気をいれ、磁気が生じモーターが回る根本にはこのマックスウェル理論がある。
さて、ニュートンの運動理論が、等速直線運動している立場からみて(先ほどの例で行けば、別の宇宙船から「先ほどの説明したように」観て、ということだが)同じように成り立つ、というのは前述した。ところが困ったことに、このマックスウェル方程式においてはそれがなりたたないのである。なりたたない。Ok big deal. それがどうした?と言われると「こうした」と答えよう。(参考文献7を参考)
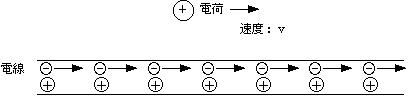
図1
電線の中を電流が流れている。電流が流れている、ということは、電線中の電子が動いている、ということだが、この電子は一挙に端から端まで流れるわけではない。動く速度は数mm/sec程度だ。
さて電流が流れているから高校でならった右ネジの法則に従って周りには磁場ができる。(さっきあげた電磁石と同じ原理だが)そこに+の電荷をぽこっと置こう。おいただけでは力は発生しないが、これを電線中を電子が移動するのと同じ速度で動かす。するとこの電荷には進行方向と垂直方向(たぶん図で言えば上方。間違っていたらごめんなさい)に力が働く。
次に同じ図柄を、電荷および電線中の電子と同じ速度で移動している観測者から見てみよう。するとこうなる。
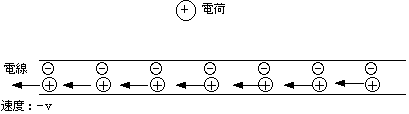
図2
さて、今度は電荷および電線中の電子は停止して見える。(同じ速度で動いているのだから当然だ)逆に電線中の+イオンが逆の方向に流れているように見える。
+イオンが流れるとはいえ、とにかく電荷が移動しているのだから電線には電流が流れていると考えて良い。(電流の流れる方向はいっしょだ。だって移動している方向は反対だが、流れているものの符合も逆だからだ)従って電線の周りに磁場は発生するが、今度は電荷が動いていないので電荷に力ははたらなかないことになる。
図1の立場では電荷に力が働き、何も支えがなければ進行方向に向かって垂直方向に動き出す。図2では力は働かないからそのままである。いま移動しているのは電線と平行の方向なのに、片方からは電荷が移動し、片方の立場からは移動しない、という観察結果が得られる、などということがあり得るのだろうか?
しかし、と私は自分自身に言う。
「それがどうした。私は知ってるんだ。相対性理論云々というからには、そのうちやれ「時計が遅れる」だの「長さが縮む」だの言い出すってことを。長さや時間が変わるんだから力の働きかたの一つくらい変わってもいいではないか。だいたい、誰が「すべての物理法則について等速直線運動している相手からみて同じように成り立つ」なんて決めたんだ。ニュートンの運動理論についてなりたつのはわかったが、だいたい位置とか速度の値は変わってる。ってことはマックスウェルの方程式くらい変わってもいいではないか。」
実際ここまでの計算はちゃんとつじつまはあっている。動いている立場から見ると電荷に働く力とか動きが変わるっていうからにはきっとつじつま合わせには苦労するのだろうけど、それだけで理論を門前払いするわけにもいかない(のだろう)
さて、ここで冒頭に述べた「科学理論とは」の定義を思い出そう。よい理論たろうとすれば、理論として客観的な論議に耐えうるとともに、「これから行う観測の結果について確定的な予測をするものでなくてはならない」ものでなければならない。
もしこの計算が正しければ、ある場合のみにマックスウェルの方程式が成り立ち、他の場合-つまりマックスウェル方程式がなりたつ立場に対して等速直線運動しているような場合-にはそこからのずれ(さっき書いたような)が観測される、と予想される。
ではそのずれはどうすれば観測できるか。
幸いなことに地球というのは太陽の周りを公転しているから、その方向というのは宇宙的にみればしょっちゅう変わっている。マックスウェルの方程式がなりたつ状態、というのがどういう状態かはしらないが、こんだけ地球の進行方向が変わっていればそれによって生ずる「ずれ」もあれこれ変化するのがわかるはずである。
というわけで、20世紀の初頭にこうしたずれを確認する実験が行われた。
ところが結果はなんとも期待はずれなものだった(だと思うのだ。その当時の人たちにとっては)そうした変化はいっさい観測されなかったのだ。
つまりここまで考えた「マックスウェル方程式+普通の見方」は「大量の観察を説明」することはできず、つまり「よい理論」とは認めてもらえないということになる。
さて、何が間違っているのだろう?可能性は以下の3つである。
1)マックスウェルの方程式が間違っている
2)マックスウェルの方程式はただしく、「普通の見方」もあっているのだが、地球はたまたまそれがなりたつ動きをしている。地球の周りを回っている宇宙船で実験すればずれが発見されるけどいつになったら宇宙旅行ができるんだろう。
3)「普通の見方」が間違っている
1)が間違っていれば実験で観察されるはずである。しかし実験の結果は「地球がどちらを向いて走っていてもマックスウェルの方程式は正しい」という意外なものだった。2)ではまるで天動説である。そしてスペースシャトルの上では電磁気の法則がずれる、という話も聞いたことがない。
となると残る可能性は3)だ。つまり我々が「普通の見方」と思っているものは、正しくないのかもしれない。それでは「正しい等速で直線運動している観測者」からの物の見方はどうあるべきなのか。また正しくないとすれば何故なのだろう。
ホーキングが「今やマックスウェル理論と光速を含むように拡張された」というからには、「光速」は「普通の見方」には従わないように聞こえる。今説明したばかりのマックスウェル方程式のように。
さて、そもそも光とは何だろう?ここでは粒子だ、波だ、という論議は細かくやらない。何度聞いても頭の上を飛び去っていってしまうし、結局覚えているのは昔子供の科学に
「アインシュタインがノーベル賞を受賞したのは相対性理論ではなかった」
という解説記事が乗っており、その中に
「光は粒とも波とも言える性質を持っており、他に何とも説明のしようがないものだと考えられて居ます」と書いてあったことを覚えているだけだ。
さて、光も早い話が電磁波である、とマックスウェル方程式が主張していることは前述した。この電磁波が伝わっていく速さは、方程式の中ではある定数で表されている。となると(例によってマックスウェルの方程式が正しいとしての話だが)つまり光はある一定の速さで伝わって行くと述べているわけだ。問題は
「誰に対して一定の速さか」
ということである。
速さの値が相手の動きかたによって、ごろごろ変わる、ということは前述した。あなたにとって止まっていると思える物体も別の立場からみれば1m/secで動いている、と見える。この値は見ている立場によって変わり、どの見方を他の見方より優先させる理由はない。(あなたがNTTソフトウェアの幹部のような独善的な人間であれば「正しいのは私の見方だ」と言えるだろうが)
従って「誰にとって」を決めなければ「一定速度」で動く、ということは言えないように思える。
さて、光が波というからにはその波を伝える何かがあるはずだ。地震であれば地面が波を伝えるし、海の波であれば海水がそれを伝える。そして水のなかであれば水が光を伝えているのであろうが、真空中でも光は伝わってくる(そうでなければ星は見えない)ということは我々が真空と思っている空間にも何かがあり、それが光を伝えているのだろう。
この「何か」がエーテルと呼ばれた光を伝える媒体である。そして前述した「光が伝わる一定の速さ」はこのエーテルに対しての速度、と考えられたのである。
ではこのような波の速度というのがどのような性質を持っているか。波の例として空気中を伝わる音をとってみよう。
たとえば音速は340m/secとする。(実はこの速度はごろごろ変わるのだが)これは何を意味しているかと言えば、音を伝えるべき空気に対して、音の波は340m/secの速さで伝わるということだ。
そこで上図のような状況を考える。空気中に音源があり、そこから340mはなれたところに人間がたっている。して、音源から「どん」と音がでると音は波となり同心円状に広がっていく。そして1秒後には人間のところに到達し「ああ。”どん”となった」と思うわけだ。
さて、上の図で人間は空気に対して静止したままで、かりに音源が動いていたとしたらどうだろう?音源と同じように動いていればさぞかし風かここちよいに違いない(これを書いているのは真夏だからそう考えるわけだが)たとえば音源の空気に対する速度を10m/secとした場合、
「どん」
となってから人間が音を聞くのは何秒後か?答えは簡単。一秒後である。音源が動こうが動くまいが空気に対する音の速度が変わるわけではない。
では別の質問。音源は空気に対して静止しているとして、人間が音源の方向に向かい10m/secで移動したとしよう。すると彼は音の速さをどう観測するか?
答えは340m/sec + 10m/secでもって350m/secである。依然として空気に対する音の速度は変わっていない。しかし今度は人間が風に髪をなびかせながら(もし髪の毛があり、しかもそよぐのに十分なしなやかさを持っているとしてだが)動いているので彼(もしくは彼女)は
340/350 秒後に自分が音を聞くことに気がつく。つまり人間が音波を伝える媒質(この場合は空気)に対して動いていると、音波の速さは異なって観測されるわけだ。
さて、話を戻そう。
「”マックスウェルの方程式で一定の速度”というのはエーテルに対する速度である」
とするのであれば、エーテルに対して観測者が移動しているとき、光速は異なって観測されるはずである。
Proof is in the puddingだかなんだか知らないが、そうして行われたのはかの有名なマイケルソン・モーレーの実験である。そしてこの「エーテルの風」を検出する実験は今日まで手を変え品をかえ繰り返されている。
原理は簡単だ。マックスウェルの方程式のところでも述べたが、地球は公転しているから運動の方向が一年を通じてずりずりと変わっていると思ってよろしい。仮にエーテルが宇宙中に充満しているとすれば、その中を移動する地球に対しては方向がずりずり変わりながらエーテルの風が吹いている、つまり光速が変わっているという事実が観測できるはずだ。
こう書くと簡単そうだが、光速というものはべらぼうに早く、そして地球の公転速度というのはそれに対しては微々たるものであるという事実を忘れてはいけない。つまり光速がかわるにしてもその割合は実に小さいのだ。ストップウォッチをもって光を発射したときにスタートさせ、遠くの鏡に反射してもどってきたときにストップさせるなんて方法では光速すらはかれないし、ましてやその微妙な変化など計りようもない。
そこで彼らは大変巧妙な実験装置を開発した。そして振動による影響を避けるため町中の交通をストップさえしたのである。
「世界で最初にエーテルを発見した人間になるのだ」
という希望に燃えたかどうかは知らない。そしてもしここでエーテルの中を地球が移動している、という実験結果が得られれば、エーテルが発見できれば(あるいは自然がそのようにできていれば)話はもっと簡単だったかもしれない。
しかしこの実験は「失敗」に終わった。それどころか「エーテルの風」を検出する試みは今日にいたるまで(ごく小数の再現できない例外を除いて)すべて失敗に終わっている。つまり真空中を伝わる光速は地球がどちらを向いていようが、どう計測しようが常に一定値なのである。
そしてこの「光速が常に一定値」でなければ現在では日常生活にも支障がでるだろう。カーナビ(うちの姉の家ではこれを「かわなび」と発音しているが)は衛星からの電波を受け取る時間差-つまり衛星から発せられた電波をうけとるまでの時間-によって位置を測定している。位置を知るのは、各衛星からの「距離」を測定しなければならないのだが、かわなびは時間差からこの距離を計算している。
この理屈が使えるのは、電波が真空中を走る速度(光の速度に等しいのだが)が常に一定だからにほかならない。でなければ
衛星までの距離=電波を受け取るまでの時間×電波の速度(=光の速度)
とすることができないか、あるいは地球のエーテルに対する速度によっていちいち補正をかけなくてはならないことになる。しかしながらいかなる「かわなび」システムもこのような補正は行っていないし、それでちゃんと位置を算出しているのだ。
さて、前述の実験結果が得られ、そしてアインシュタインが発表した特殊相対性理論が広く受け入れられるようになるまでの間、ありとあらゆる「実験結果の説明」がなされた。それは
「エーテルの風が観測されない、ということは、全宇宙を満たしているエーテルは常に地球とともにある。つまり地球は宇宙の中心にある。天動説万歳!」
というものから、
「地上ではエーテルの濃度が濃く、地球と一緒になって動いてしまっているので風が計測されないのだ」
というものまであった。後者については「かわなび」の原理を考えればあたらないことが解ってもらえると思う。「かわなび」が発明されていなかった当時でも実際にエーテルが薄い丘の上で同様の実験が行われたが結果は同じく
「エーテルの風速=0」
であった。
となると何かがおかしい、という結論に達せざるをえない。ここで取られた一つのアプローチというのが
「今までの文章の中では「普通の見方」と思っていた物は、実は正しくないのではないか」
というものである。つまり実験結果を説明できるように、「普通の見方」を変更してやろう、というのである。こうしたアプローチからしかるべき変換式が導ける、というのは私のような怠け者にとっては一種信じがたいことだ。しかし物理の少なくとも2カ所(私が知っている範囲で)に名前を残しているローレンツという男はこの変換式を導いてしまった。
その変換式によれば、エーテルの風の中を進むときは物体の長さが縮むのである。またその時計も遅れる。彼には何故そうしたことがおこるかについて、うまく説明はできなかったが、とにかくこう仮定すると実験結果をうまく説明することができるのである。
具体論でいこう。たとえばある長さの腕の先に鏡がついていて、腕の根本からその鏡に対して光を発射。反射されて戻ってくるまでの時間を測定するとしよう。
さて、上図のような状況を想定する。光源と鏡の間の距離はなんと15万km、光速は30万km/secとしよう。でもってエーテルの流れが(これまたすさまじいのだが)18万km/secとする。
光源からみれば、鏡のほうからエーテルの暴風が吹いているような状況なのだが、実際にはなにも感じない。(だってエーテルは光を伝える以外になにも物理的な性質をもっていないんだもん)しかしながら光を鏡に向かって照射するとおこることは以下のようになる。
1)光は30−18=12万km/secで鏡に向かってのろのろ進む。本来もっと早いのだが、すごい逆風が吹いているからしょうがない。鏡に到達するのは15/12 = 1.25秒後
2)鏡で反射した光は今度は追い風をうけて30+18=48万km/secのスピードでもといた位置に向かう。鏡から光源まで到達するのに必要な時間は15/48 = 0.3125秒後
合計所用時間は1.5626秒であるからして平均速度は30万km/1.5625=19.2万km/sec
(もちろん行きが(30-18)万km/sec、帰りが(30+18)万km/secだから平均は(12+48)/2で変わらず30万km/secというのは間違いである。多分これは小学校か中学校の問題ではなかろうか)
かくのごとくエーテルの風が吹いていれば光速は変化して観測されるはずなのだが、さかさにしようがどうしようがこの変化は検出できない。そこでローレンツが考えた「説明」というのは概略以下のようなものである。
この図では棒というのは圧縮方向にエーテルの風をうけている。したがって縮んで長さが短くなっている。細かい計算はすっとばすが、80%の長さになっていると考える。つまり光源と鏡の間の距離は12万kmに縮んでいる、、、、のだがこれは実はなかな測定しずらい。本人が
「なに?長さが縮んでるって?よしでは巻尺で(15万km)はかってみよう」
としたところで、巻尺の同じく80%の長さに縮んでしまっているから、彼は
「ちゃんと15万kmあるよ」
とむきになって反論する。つまりこの「縮み」は計測にかからない。
さて、かくのとおり腕が縮んだとすると光源から放たれた光は1.25秒後に戻ってくる。しかし光源にいる人間はあくまでも
「腕の長さは15万km」
と思っているから30/1.25 = 24万km/secの平均速度で光が伝わったと見る。ということはこれではまだ「説明」になっていない。なんとしても1秒で戻ってきてもらえないことには
「光速はやっぱり30万km」といえないのである。
さて、こうした状況を打開するにはプロレスのレフェリーを思い出せばよい。勝つべき人間がフォールされているときに、3カウントをさけるためにはカウントをゆっくりとればいいのだ。というわけで、
「エーテルの風をうける人間の時計はゆっくり進む」
という仮説を導入しよう。この割合は(これも細かい説明は省略するが)時間が1.25倍にのびるということになる。つまり
「あの野郎。おれの時計で1.25秒たったときにようやく1秒とかぞえやがった」
という状況だ。これでめでたく問題解決。エーテルの風を受けている立場では、確かに光速は変化しているのだが、腕の長さが縮みまた時計がゆっくり進んでいるので
「光は30万kmを1秒で往復した」
と観測し、光速は30万kmのままなのである。
かくのごとく、「なんでそうなるんだ」というのは今一つ釈然としないが、とにかくこのように物が縮んだり、時間が遅れたりすると計測結果をちゃんと説明することは可能なのである。
こう書くと「なんだ。それは相対性理論の帰結そのものではないか」と思われるかもしれないが、まさにその通り。ここまで「普通の物の見方」と呼んでいる物は「ガリレオ変換」と呼ばれるが、特殊相対性理論で言うところの物の見方は「アインシュタイン変換」ではなく「ローレンツ変換」と呼ばれる。つまり実験結果を説明するためにローレンツが導いた「つじつま合わせ」の数式は今日においても正しい物と考えられているのだ。
では何故ローレンツはアインシュタインほど有名ではないか。アインシュタインが他に成し遂げた成果を別にしても(ローレンツだってこの研究ばかりしていたわけではない)それにはちゃんと理由がある。
この説明はどう見ても
「がんばってこじつけた」
という気がするからだ。そりゃ確かに実験結果をちゃんと説明はしているが、、、、前述のホーキングの言葉にあった
「作為的な要素を少ししかふくまず」
というのに果たしてあてはまっているんだろうか。
そもそもエーテルの風をうけると物質が縮むとはどういうことか?ローレンツは電場と磁場の中で運動する電荷に働く力に「ローレンツ力」として名を残している人でもある。そして物質を構成する原子の構成-つまるところはマイナスの電子と+の陽子だ-とエーテルの中での振る舞いを考え、確かにエーテルの風の中では物体が縮むであろう、ということを導き出した。しかしこれは電磁気の性質をベースにした考察だから、たとえば
「静止エーテル中で、A地点から10km離れた場所に的がある。今A地点を的に向かって秒速15万kmで移動する物体が通過した。さて、この物体からみると的は何km先にあるでしょう?」
という問題に対しては「10km」という答えをだす。だってA地点と的の間には何もないから陽子が電子がどうしようが縮みようがないではないか。(先ほどの例のように腕で支えられているわけではないのだ)そして実はこの結論は正しくない。
正直言えばこうした結論をローレンツがいかに導いたか、そしてその辻褄合わせをどのように行っていったかはたぶん大変興味深い物語なのだと思う。残念ながら私は当時の論文などに直接あたることはできないが、あれこれ解説書を読んでみるとこの「ローレンツ変換」はかならずしも広く受け入れられたわけではないようだ。
では今日広く受け入れられている相対性理論とは何が違ったのか。結果として出てくる変換式は同じなのに。
注釈
電場:E、磁束密度:B、電荷密度:ρ、電流密度:j、真空の透磁率:μ、真空の誘電率:ε
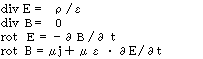
と書き表される。ところがこれにガリレオ変換 x' = x − Vt, t' = tを当てはめると
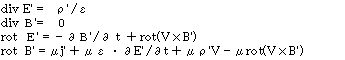
となり、元の方程式と異なった形になってしまう。本文に戻る
確認する実験:上記の「ガリレオ変換をかけたマックスウェル方程式」の3番目にはrot(V×B')という項がある。この項があると以下のような現象が観測されると予測された。
棒の両端に+と-の電荷をつけると、それぞれはひっぱりあうのだが、別に回転するなんてことはない。しかし棒がエーテルの中を動いていると「余分な項」が働き、棒が回転する。
この実験は1903年に行われTrouton-Nobleの実験と呼ばれているが、いつ観測してもこうした棒の回転は観測されなかった。本文に戻る
速度が変わるわけではない:動く方向によっては周波数-つまり音の高さ-は変わりうる。仮に人間のほうに近づいてくるとすれば音は高くなる。所謂ドップラー効果によって。本文に戻る
補正をかけなくてはならない:もっとも「NASAは補正をかけた電波を発していて、その事実を隠蔽している。エーテルの風は吹いているのだ」と主張する人も存在する。本文に戻る
丘の上:本当は「エーテルが薄い」なんて説明ではなく「地球が光を伝える媒質(それがあればだが)に対して移動している事を示している光行差が観測される丘の上」ということなのだが。本文に戻る